
初心者向けのブログになります!
当社のお問い合わせより定期的に写真のような波型プラグの完成品を
購入後に「どうやって挿すの?」「バナナプラグであってる?」といった
お問い合わせを頂きますので当社プラグを使って解説していきたいと思います。
アマゾンなどでも大半は「提灯タイプ」のバナナプラグ!

画像は当社のBP-146Gですがアマゾンの人気バナナプラグは
ほとんどこの「バナナ」にも「提灯」にも見えるバナナプラグになります。

接続方法は画像上のように穴の先端を先っぽを入れて
奥に強く押し込めば差し込める仕様となっております。
こちらのプラグが昔からあり、皆さん馴染みのあるプラグかと思います。
オーディオ向けに作られたであろう波型BFAタイプ!

画像の通り、「提灯」のような形ではなく「BFA波型」で提灯タイプより
接地面積が多いこと、耐久性があることで抜き差しが多い
オーディオファンに人気のプラグとなります。
提灯タイプはプラグの真ん中の部分しか接地面積がありませんが
BFA波型は全面に近い接地面積なので通電性にも有効とされています。
また耐久性ですが提灯タイプは銅の(バネ性)を利用した構造です。
しかし銅のバネ性は弱く、長年刺していると真ん中の膨らみが
戻らなくなり、次回、挿す際はスカスカになってしまいます。
抜き差しにも弱く、ケーブルのブラインドテストにも不向きです。
その点、BFAタイプは波型スリットを入れ、弾性(戻ろうとする力)を利用して
差し込むプラグなので変形しにくく、抜き差しに対する耐久性も高くなります。
BFA(波型)プラグの差し込み方!

画像は当社のBP-312GCになりますが(燐青銅製)であれば柔らかいので
提灯タイプ同様、押し込みだけで差し込みできます。

ただ当社のBP-208シリーズはベリリウム製でできており、ベリリウムは
燐青銅より硬いので画像のように先端を指でつまみながら先端を入れた後に
押し込むと比較的スムーズに入ります。
ただ結構硬いので指に力を入れて、覚悟して装着して頂ければと思います。
知っていると思いますがついでにYラグ画像も載せときます!

バナナジャックを左に回すと緩んでいき、Yラグ分、隙間が空けば
Yラグを差し込んでジャックを右に回して締めると接続完了です。
画像の通り、下から差し込む方が多いとは思います。
接続が非常に簡単でバナナでは製造できない「純銅製」プラグも
Yラグでは製造可能なので好んで使う方も多くいらっしゃいます。
ですがデメリットとしては純銅は柔らかいので「ねじ止め時の固定する力が弱い」
ので重たく太い線には不向きであったり、ケーブルが下に出るので
アンプの位置によっては台と干渉する恐れなど計算して
配置しなければなりません。
以上いかがでしたでしょうか?
ずっと書きたかった記事だったのでようやくかけてスッキリしております。
バナナジャックも記事のために、アマゾンで知らない業者から購入しました。
初心者オーディオファンのお役に立てれば幸いです。
またバナナジャックもONKODO製のものを制作予定です。
ご意見などあればお問い合わせよりお聞かせ頂ければ幸いです。
以上プラグQ&Aでした。


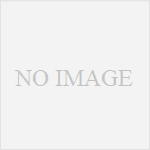
コメント
波型BFAタイプとバナナ型の違いがよくわかりました。早速波型BFAタイプを購入しようと思っております。